戞侾愡丂愴壥偲懝奞
堦斒揑偵乽帺孯偺懝奞曬崘偼傾僥偵側傞偑愴壥曬崘偼傾僥偵側傜側偄乿偲偝傟傞丅
偦偙偱崱夞偼僲儌儞僴儞帠曄傪椺偵庢傝丄斵変偺懝奞曬崘偲愴壥曬崘偺僘儗傪峫嶡偡傞丅
僲儌儞僴儞帠曄偼侾俋俁俋擭俆寧侾侾擔偵杣敪偟摨擭俋寧侾俆擔偵掆愴偟偨擔僜椉孯偺崙嫬暣憟偱偁傞丅
偊偭丄偨偐偑崙嫬暣憟儗儀儖偱偼嶲峫偵側傜側偄偭偰丠
偦傫側帠偼側偄丅
僲儌儞僴儞帠曄偼擔杮棨孯峲嬻戉偵偲偭偰乽偲偰偮傕側偄戝愴乮僆僆僀僋僒乯乿偩偭偨丅
擔杮棨孯愴摤婡搵忔堳傪挷傋傞帪偺僶僀僽儖偲傕尵偊傞峲嬻忣曬暿嶜乽擔杮棨孯愴摤婡戉乿傪傂傕偲偙偆丅
偙偙偵偼擔杮棨孯偺僄乕僗堦棗偲宱楌偑偁傞偑丄偙傟偵傛傞偲俀侽婡埲忋寕捘偟偨搵忔堳偼俀俁柤偍傝丄偦偺僗僐傾傪崌寁偡傞偲寁俇俁侽婡偲側傞丅
偦偟偰偦偺偆偪係侾俇婡偑僲儌儞僴儞帠曄偱偺僗僐傾偲側偭偰偄傞偺偱丄懢暯梞愴憟偱偺僗僐傾偼側傫偲俀侾係婡偩偗偩丅
乮擔壺帠曄偱僗僐傾傪嫇偘偨僄乕僗偼壛摗寬晇彮彨丗侾俉婡傗峕摗朙婌彮嵅丗侾俀婡側偳偛偔彮悢偱偁傝丄俀侽婡埲忋僄乕僗偱偼侾柤傕懚嵼偟側偄乯
徍榓侾俇擭侾俀寧偐傜徍榓俀侽擭俉寧侾俆擔傑偱係係儢寧懕偄偨懢暯梞愴憟偑俀侾係婡偱偨偭偨係儢寧乮嬐偐侾乛侾侾偺婜娫両乯偺僲儌儞僴儞帠曄偑係侾俇婡丠
懢暯梞愴憟偱偼棨孯峲嬻戉偺嬻愴偑峴傢傟側偐偭偨偺偩傠偆偐丠
偦傫側帠偼側偄丅
奐愴捈屻偺僼傿儕僺儞峲嬻愴傗儅儗乕峲嬻愴丄棖報峲嬻愴丄偦傟偵懕偔價儖儅峲嬻愴傗僜儘儌儞丄僯儏乕僊僯傾峲嬻愴丄僼儔僀儞僌僞僀僈乕僗偲愴偭偨拞崙峲嬻愴丄枛婜偵巰摤傪孞傝峀偘偨僼傿儕僺儞峲嬻愴傗戜榩丄壂撽峲嬻愴側傜傃偵杮搚杊嬻愴丅
悘暘偲嬻愴偼偁偭偨偼偢偩丅
偩偑僩僢僾僄乕僗俀俁柤偵傛傞侾儢寧偁偨傝偺寕捘婡悢偱尵偊偽懢暯梞愴憟偑俆婡庛側偺偵懳偟丄僲儌儞僴儞帠曄偼侾侽係婡偱俀侽攞傪墇偊傞丅
乽僜楢婡偼僠儑儘僀偐傜偹丅暷塸孯婡偲偼斾傋暔偵側傜側偄傛丅乿偲偐乽偒偭偲懢暯梞愴憟偺僄乕僗偼俀侽婡枹枮偵僊僢僔儕傂偟傔偄偰偄傞偺偩側丅乿偲尒傞偺傕傂偲偮偺峫偊曽偱偁傠偆丅
偟偐偟偙偙偱乽僲儌儞僴儞偱偺愴壥曬崘偼偪傚偭偲夦偟偔側偄偐丠乿偲峫偊傞偺傕廳梫偱偼偁傞傑偄偐丠
偄偢傟偵偟偰傕擔杮棨孯峲嬻戉偵偲偭偰僲儌儞僴儞帠曄偑乽偲偰偮傕側偄戝愴乿偱偁偭偨偺偼帠幚偱偁傞丅
側偵偟傠僲儌儞僴儞帠曄杣敪摉帪丄擔杮棨孯偺愴摤婡晹戉偼侾侽屄愴戉乮戞俆愴戉傗戞侾俁愴戉側偳偺楙廗晹戉傪娷傓丅偙傟傜偺晹戉傗戞係愴戉偼侾屄拞戉偟偐愴摤婡傪曐桳偟偰偄側偄偟戞侾愴戉傗戞俀係愴戉丄戞俆俋愴戉偼俀屄拞戉曇惉偱偁傞丅乯偲侾屄撈棫拞戉偱俀俁屄拞戉乮俋俈愴亊侾俆屄丄俋俆愴亊俉屄丗摉帪偼侾屄拞戉栺俋婡偩偭偨偺偱搵忔堳偺奣悢偼栺俀侽侽柤乯偩偭偨偑丄偙傟傜偺偆偪俀侽屄拞戉乮俋俈愴亊侾係屄丄俋俆愴亊俇屄乯偑僲儌儞僴儞傊搳擖偝傟侾侽侽柤嬤偄愴摤婡搵忔堳傪幐偭偰偟傑偭偨偺偩偐傜丅
摿偵愴摤婡巜婗姱偺懝栒偼寖偟偔愴巰幰偩偗偱彮嵅侾丄戝堁俉丄拞堁侾侽偵媦傇丅
乽傆偆傫丄愴摤婡晹戉偠傖嵅姱偺愴巰幰偼侾柤偩偗偐丅乿偲巚偭偰偼偄偗側偄丅
搳擖偝傟偨俈屄愴戉乮侾丄俋丄侾侾丄俀係丄俁俁丄俆俋丄俇係乯偺偆偪俁俁愴戉偑愴応偵偄偨偺偼侾俇擔丄俆俋愴戉偼俇擔丄俋愴戉偼俁擔偩偗側偺偱丄愴偄懕偗偨係屄愴戉偵尷傟偽侾侾愴戉傪彍偔俁屄愴戉慡偰偱愴戉挿偑寕捘偝傟晧彎偟偰偄傞偺偩丅
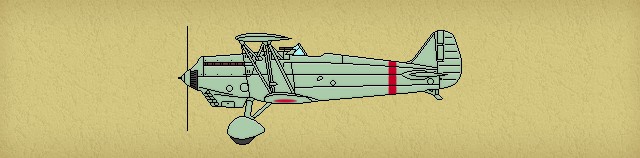 |
| 俋俆幃愴摤婡 |
摿偵戞侾愴戉偱偼俈寧侾俀擔偵愴戉挿偺壛摗拞嵅偑晧彎偟丄俀俋擔偵偼屻擟偺尨揷彮嵅偑弶恮偱愴巰丄嵟廔揑偵偼慡拞戉挿偲慡彨峑偑巰彎偡傞偵帄偭偨丅
懝奞偑懡敪偟偨偺偼戞侾愴戉偽偐傝偱偼側偄丅
楌愴係屄愴戉乮寁侾侾屄拞戉乯偱傒傟偽拞戉挿侾侾柤拞俋柤偑巰彎偟丄偦偺屻擟拞戉挿傗拞戉挿戙棟払傕懕偄偰尙暲傒巰彎偟偰偄傞丅
僲儌儞僴儞帠曄偱偺巜婗姱戝検憆幐偑偦偺屻偺擔杮棨孯愴摤婡戉偵戝偒側塭嬁傪媦傏偟偨帠偼尵偆傑偱傕側偄丅
戞俀愡丂僲儌儞僴儞峲嬻愴偺奣棯
偦傟偱偼帠曄偺悇堏偵偮偄偰偁傜傑偟傪弎傋傛偆丅
侾俋俁俋擭俆寧侾侾擔丄擔僜偳偪傜偐偺孯偑墇嫬偟偰崙嫬暣憟乮戞侾師僲儌儞僴儞帠曄乯偑杣敪偟偨丅
偙偺嵺丄偦傟偑乽偳偪傜偐偱偁傞帠乿偼偳偆偱傕椙偐偭偨丅
梫偼偳偪傜傕乽戅偔婥偼側偄偭偰帠乿偑廳梫偩偭偨偺偱偁傞丅
偐偔偟偰帠曄偼奼戝偟偨丅
棨愴偵偮偄偰彂偔偲挿偔側傞偺偱埲崀偼峲嬻愴丄摿偵愴摤婡晹戉偵偮偄偰偩偗弎傋傞丅
嵟弶丄僲儌儞僴儞偵偄偨僜楢峲嬻晹戉偼戞俈侽愴摤婡楢戉乮僓僶儖乕僄僼彮嵅丗俁俉婡乯偲戞侾俆侽敋寕婡楢戉乮俀俋婡乯偲偦偺懠侾俆婡乮僲儌儞僴儞慡愴巎偱偼侾俈婡乯偐傜側傞戞侾侽侽崿惉旘峴抍偱偁偭偨丅
偦偙偱娭搶孯偼惂嬻尃傪摼傞偨傔侾俁擔偵戞俀係愴戉乮俋俈愴俀屄拞戉乯傪搳擖偟偨丅
戞俀係愴戉偼侾俉擔偐傜彛夲傪奐巒偟俀侽擔偵偼弶寕捘乮掋嶡婡乯傪婰榐偡傞丅
僜楢懁偲偟偰傕栙偭偪傖偄傜傟側偄丅
俀俀擔偵偼戞俀俀愴摤婡楢戉乮僌儔僘僀僉儞彮嵅丗俇俁婡乯偲戞俁俁敋寕婡楢戉乮俆俋婡丗偨偩偟俁俉敋寕婡楢戉偲婰弎偡傞帒椏傕偁傞乯傪孞傝弌偡丅
俀係擔偵偼晧偗偠偲擔杮孯偑侾侾愴戉偺敿悢乮俋俈愴俀屄拞戉乯傪恑弌偝偣偨丅
傕偼傗僲儌儞僴儞忋嬻偼戝嬻愴偱偁傞丅
偙偺愴偄偼擔杮孯偑彑偭偨丅
擔杮偑庡挘偡傞愴壥偲僜楢偑敪昞偡傞懝奞偱怘偄堘偄偑尒傜傟傞傕偺偺丄俆寧拞偵寕捘偝傟偨偺偼俀俉擔偵岝晉拞堁偑棊偲偝傟偨偩偗偱偁傝丄僜楢懁傕愴壥偑侾婡偟偐柍偄帠偲晧偗偨帠傪擣傔偰偄傞偺偩偐傜丅
俀俋擔丄婋婡姶傪書偄偨僜楢孯偼杮崙偺僗儉僔働乕價僢僠嬻孯暃杮晹挿偑係俉柤偺儀僥儔儞愴摤婡僷僀儘僢僩傪棪偄偰椃媞婡俁婡偱儌儞僑儖偺慜慄偵忔傝弌偡丅
偮偄偱俁侽擔丄擔杮偺戞侾侾愴戉偺巆晹乮俋俈愴俀屄拞戉乯偑恑弌偟偨丅
乽偙偺傑傑帠懺偑悇堏偟偰偄偔偲僲儌儞僴儞偼峲嬻婡偩傜偗偵側傞側乿偲巚傢傟偨偑丄俇寧俀擔偵戞侾師僲儌儞僴儞帠曄偼廔寢偡傞丅
廔寢偲尵偆偲乽偁偁丄掆愴岎徛偑奐嵜偝傟偰僴僫僔偑偮偄偨偺偩側丅乿偲巚傢傟傞偐傕抦傟側偄丅
偱傕擔杮孯偑棨忋晹戉傪偪傚偭偲屻曽傊戅偄偨偩偗偱僜楢偲偟偪傖壗傕暣憟傪廔偊偨偮傕傝偼側偐偭偨偺偩丅
憡曄傢傜偢僜楢偼暫椡偺憹嫮偵搘傔傞偺偱丄俇寧侾俈擔偵偼摉慠偺擛偔戞俀師僲儌儞僴儞帠曄偑杣敪偡傞丅
崱搙偼擔杮孯傕暫椡傪彫弌偟偵偼偟側偄丅
俇寧侾俋擔丄戞俀旘峴廤抍乮愴摤婡偼戞侾丄侾侾丄俀係愴戉丗崌寁俋俈愴俉屄拞戉乯偵揥奐柦椷偑壓偝傟傞丅
偐偔偟偰擔僜椉孯偼嵞傃寖楏側峲嬻愴傪孞傝峀偘俀俀擔偵偼僌儔僘僀僉儞彮嵅丄俀係擔偵偼僓僶儖乕僄僼彮嵅偑愴巰偟偨丅
偙偺梋惃傪偐偭偰敪摦偝傟偨偺偑俇寧俀俈擔偺戞侾師僞儉僗僋嬻廝偱偁傞丅
僜楢孯旘峴応傪暍柵偡傞偙偺嶌愴偵擔杮孯偼掋嶡婡侾俀婡丄愴摤婡俈係婡丄寉敋俇婡丄廳敋俀侾婡偺崌寁侾侾俁婡傪搳偠丄俋俉婡寕捘乮擔杮棨孯愴摤婡戉偵傛傞悢抣丗捯嶲杁偺庤婰偵傛傞偲抧忋寕攋傪娷傔侾侾係婡偲偟偰偄傞丗娵俇係俉崋偱偼抧忋寕攋傪娷傔侾侾侽婡丗悽奅偺愴摤婡戉偱偼侾係侽婡乯偺愴壥乮嶌愴偵嶲壛偟偨戞侾侾愴戉偺戨嶳拞堁偱偡傜乽偲偰傕偦傫側悢帤偵偼側傜側偄偼偢偱偡乿偲岅偭偰傞偑乯傪曬偠偨丅
偨偩偟摉帪偺僜楢孯暫椡偼嬻廝捈慜偱愴摤婡侾俆侾婡丄敋寕婡侾侾俇婡偺寁俀俇俈婡偵夁偓偢丄嬻廝偵傛傞懝奞偼侾係婡乮娵俇係俉偺悢抣乯偲偟偰偄傞丅
嵟弶偼乽晧偗乿傪擣傔偰偄偨僜楢孯偼偙偺崰偐傜乽愴壥乿傪庡挘偟巒傔丄椉孯偺愴壥敪昞偼戝偒側僘儗傪帵偟弌偡丅
偝偰椉孯偼傑偡傑偡愴椡傪憹嫮偡傞丅
俈寧俀侾擔丄僜楢偼戞俆俇愴摤婡楢戉傪恑弌偝偣俉寧侾俆擔偵偼擔杮偑戞俇係愴戉乮俋俈愴俁屄拞戉乯傪搳擖丅
偦偟偰俉寧俀侾擔偵偼戞俀師僞儉僗僋嬻廝丄俀俀擔偵偼戞俁師僞儉僗僋嬻廝偑敪摦偝傟偨偑丄俈寧侾俀擔偵壛摗拞嵅乮戞侾愴戉丗晧彎乯丄俈寧俀俋擔偵尨揷彮嵅乮戞侾愴戉丗愴巰乯丄俉寧係擔偵偼徏懞拞嵅乮戞侾愴戉丗晧彎乯偲奺愴戉挿埲壓丄搵忔堳偺巰彎偑憡師偄偩丅
傕偼傗慜慄偺擔杮孯晹戉偼僘僞僘僞偱偁傞丅
偙偺寠傪杽傔傞堊丄俉寧俁侽擔偵偼戞俁俁愴戉乮俋俆愴俁屄拞戉乯丄俋寧俋擔偵偼戞俆俋愴戉乮俋俈愴俀屄拞戉乯丄俋寧侾俀擔偵偼戞俋愴戉乮俋俆愴俁屄拞戉乯偲峏側傞憹墖偑孞傝弌偝傟偨偑丄傕偼傗俋俈愴晹戉偼暐掙偟偰偍傝憹墖偺庡椡偼暋梩偺俋俆愴晹戉偲惉傝壥偰偰偄偨丅
側偍嵟廔婜丄僜楢孯偼戞侾俋丄俀俀丄俀俁丄俆俇丄俈侽偺俆屄愴摤婡楢戉傪梚偟偰偄傞丅
偦偟偰俋寧侾俆擔偺戞係師僞儉僗僋嬻廝傪傕偭偰峲嬻愴偼廔傢傝傪崘偘丄摨擔惉棫偟偨掆愴岎徛偵傛偭偰僲儌儞僴儞帠曄偼偦偺枊傪暵偠偨偺偱偁傞丅
戞俁愡丂壩椡偲杊屼椡偺斾妑
偙偙偱椉孯偺庡椡愴摤婡偲側偭偨擔杮孯偺俋俈幃愴偲僜楢孯偺俬亅侾俇傪彮偟斾妑偟偰傒傛偆丅
|
|
憃曽偲傕侾俋俁侽擭戙屻敿傪戙昞偡傞掅梼扨梩偺扨敪愴摤婡偩偑丄俋俈幃愴偑屌掕媟丄俬亅侾俇偼夝曻幃僉儍僲僺乕偲尵偆寚揰傪傕偭偰偍傝嵟崅懍搙偼摨掱搙偱偁傞丅
傑偨俋俈幃愴偼塣摦惈偑桪傟偰偄偨偑壩椡偲杊屼椡偑庛偔丄俬亅侾俇偼塣摦惈偑埆偄傕偺偺壩椡偲杊屼椡偑嫮偐偭偨丅
偦傟偱偼俋俈幃愴偲摨帪婜偵奐敪偝傟偨奺崙愴摤婡偺壩椡傪楍婰偟偰傒傛偆丅
俋俈幃愴偼侾俋俁俆擭侾俀寧偵奐敪偑奐巒偝傟侾俋俁俇擭侾侽寧偵帋嶌婡偑弶旘峴偟丄侾俋俁俈擭侾俀寧偐傜検嶻偝傟偨俈丏俈噊婡廵俀栧傪憰旛偡傞扨敪扨嵗愴摤婡偩丅
傑偢僪僀僣偱憡摉偡傞愴摤婡傪扵偡偲侾俋俁俆擭俋寧偵帋嶌婡偑弶旘峴偟偨俛倖侾侽俋偑偙傟偵憡摉偡傞丅
俛倖侾侽俋偼帋嶌婡抜奒偱偼俈丏俋俀噊婡廵俀栧偺寉晲憰偩偭偨偑丄弶偺検嶻宆乮侾俋俁俈擭俁寧乯偱偁傞俛宆偱偼俈丏俋俀噊婡廵俁栧偲側傝丄侾俋俁俈擭枛偐傜惗嶻偑奐巒偝傟偨俠宆偱偼俈丏俋俀噊婡廵係栧偵嫮壔偝傟偨丅
|
| 偍帋偟斉偼偙偙傑偱偲側傝傑偡丅 慡偰廂榐偟偨僼儖僶乕僕儑儞偼暰幮捠怣斕攧偵偰偛峸擖偄偨偩偗傑偡丅 |